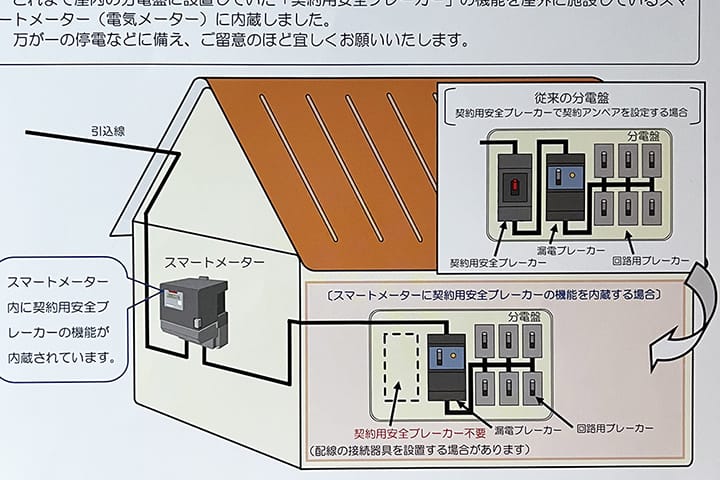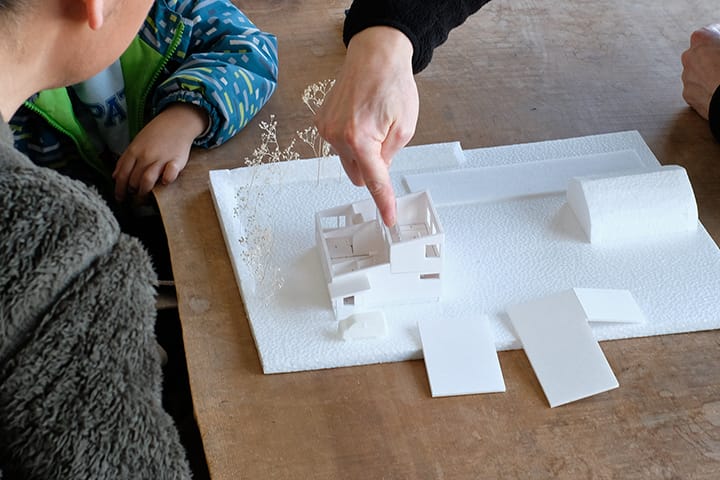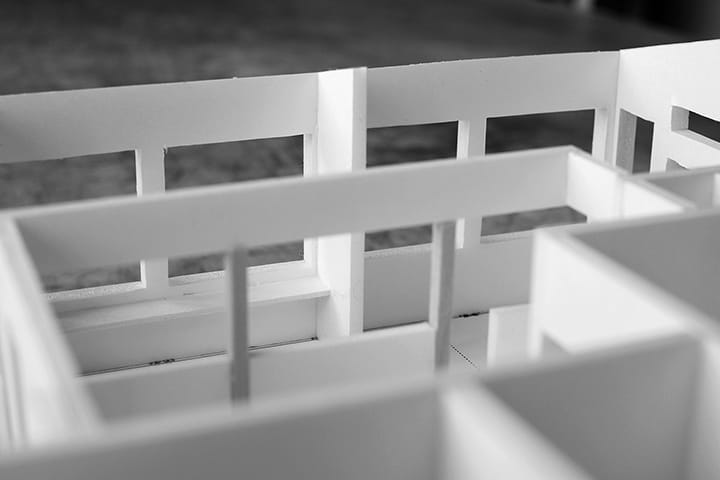昨年12月に札幌市内の新築住宅が完成しました。
そしてお引越しされて数日後、薪ストーブの火入れ初め(火入れ式)に立ち合わせていただきました。

薪ストーブ工事は、札幌市内の薪ストーブ店「北海道リンクアップ」に依頼しました。
また、すぐに焚ける乾燥済みの広葉樹薪も2立方メートル届けてもらっています。玄関のすぐ脇、それから裏面の2箇所に分けて積み上がっていました。
薪ストーブがメイン暖房の家ではないので、これで冬1シーズン足りるかもしれません。

選ばれた薪ストーブは、パークレイのアスペクト8(PARKRAY ASPECT8)。
薪を使ったクッキングストーブのメーカーとして始まったルーツがパークレイにはあり、ストーブトップでの湯沸かしや煮炊き、炉内にダッチオーブンや鋳物ホーローSTAUBを入れて薪ストーブクッキングが楽しめるように作られている。
実際にアスペクト8のガラス扉はこの通り、幅60センチくらいと大きくて、薪やクッキング鍋が楽に出し入れできそう。

北海道リンクアップの加藤さんに取り扱い説明をしていただきながら、火入れ初め。
火をつける前にいくつか確認と準備が必要です。
まずは薪ストーブのある室内の負圧を和らげること。
負圧とは周りの気圧より、低い気圧状態のことです。
室内が負圧の状態だと、煙突から外気が入ってきて、焚き付けの際に煙が室内に広がってしまう。
換気扇を止めたり、近くの窓を開けたりすることで、室内の気圧を調整できます。
薪ストーブの扉を少し開けて、チャッカマンやマッチの炎のなびく向きを確認しましょう。
炎が薪ストーブの内部側に吸い込まれるようになびくようになったら、焚き付けしても大丈夫です。

次に基本的な薪の組み方について。
薪と薪は1〜2センチほど隙間をあけて井桁に組む。空気が通る適度な隙間があるとよく燃えるそうです。
その上に焚き付け用の小割り材を同様に積み載せる。

室内の気圧が整う間に、薪を炉内に組んでおきます。

そして、いよいよ薪に着火。火入れ初めです。
着火後しばらくは扉を少し開けて直接空気を送り、焚き付けを助ける。
まだ焚き付け材が燃えているだけで、260℃以上の温度をしばらく維持しないと薪自体は燃え始めません。

5〜10分経って、しだいによい感じに炎が立ち始め、燃え上がっていきます。
パチパチと薪がはぜるかすかな音が聞こえ、木の燃える独特の香りが漏れて漂う。

このパークレイ アスペクト8は、実にシンプルなフォルムでガラス面が大きく、薪と炎が強調されてより美しいと感じられる。
新居ともども、これから始まる薪ストーブライフ。ゆったり気ままに楽しんでいただけると誠に幸いです。